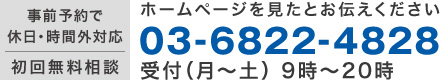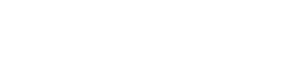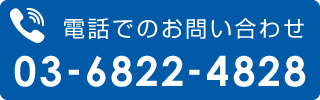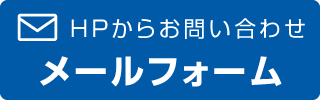Posts Tagged ‘節税’
税理士へ依頼したつもりが税理士でなかったんです!
先日、ご契約頂いた法人のクライアントが、今迄お願いしていた方が税理士ではなかったと、解約の
時に気付いたらしいです(苦笑)
20年近く依頼をしていたらしいのですが、、、、
この様に税理士を装った「にせ税理士」に関しては国税庁のホームページにも、「にせ税理士にご注
意」といった案内があるくらい、にせ税理士は多いようです。
参照:国税庁ホームページ「No.9204 にせ税理士にご注意」
税理士は税理士会へ登録することになっていますので、契約する際には、「税理士 検索」でネット
検索し理士会へ登録している税理士かどうかご確認ください。
本名を知っているのならば、日本税理士会連合会の「税理士情報検索サイト」で検索してみるのが
良いかと思います。この税理士情報検索サイトは、名前を漢字で検索するときは「完全一致」でな
いと検索できない為、漢字が分からない場合にはカタカナで検索なさってください。
また、申告書にサインできませんので、申告済の申告書の控えを見ると、税理士かどうか分かるか
もしれません。税理士署名欄が空欄や知らない人の名前があった場合には、「にせ税理士」かもし
れません。
にせ税理士に依頼して困ることとはあるのか?
にせ税理士に依頼しても、依頼者側は困らないからいいじゃないと思う方もおられるかと思います。
にせ税理士は料金安めのことも多いようで、依頼者には「安くてよくやってくれるし、働きぶりに
満足していたよ」と聞いたこともあります。
しかし、ある日突然、「連絡が取れなくなった」ということもあるようです。
また、おかしな節税(ほぼ脱税)の様な提案もしてくることもあるようで、追徴課税時には姿を消
すこともあるようで、、、、
自社を守る為にも、にせ税理士にはご注意ください。

当事務所は墨田区を拠点に、東京、千葉、神奈川、埼玉の首都圏を中心に対応していますが、ご依頼があれば全国対応も可能です。
会計事務所での勤務経験と元システムエンジニアとしての経験を活かし、税務・経営相談だけでなく、業務効率化やシステムサポートなど、幅広いサポートを提供しています。
初回のご相談は無料、事前予約で休日・時間外の相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
Question:会社で預金を増やすべきか、運用をすべきか迷ってます。
Answer
経営状況の良好な会社では、利益が生じ、納税後も純資産は上昇していきますね。
黒字になり、預金が増えていくと色々な案を検討するケースもあります。
基本的に私のお客様へは、以下の様なステップでご提案等をしております。
①安全保有預金残高の確保
まず、会社経営に必要なランニングコストを算出し、企業毎に併せて確保すべき
預金残高を計算し、クリアしているかの確認。クリアしている場合には②へ
②新規事業展開か、現状事業の維持又は拡大か。
新規事業展開の場合にはイニシャルコストが生じます。この場合の事業計画を策定し
保有資金で進めるか融資を受けるかの検討をします。
現状維持・拡大の場合には、新規事業展開ほどのイニシャルコストは必要無いケース
が多いですが、事業計画の作成はします。
③現預金が余る場合の資産ポートフォリオの作成
現状、インフレ率が2%~3%という中で今の100万円は将来同じ価値を持たないこと
となります。(今100万円で購入できるものが、来年は102万円以上となるイメージ)
預金利率を超えるインフレ率である事から、預けているお金は目減りしている事と
同じです。
そこで、運用や節税を図る事で、営業活動で増加する預金とは別に、今ある預金を
その他の資産に変える事で目減りを止め、更には増加させるという内容です。
具体的な方法としては、証券会社や生命保険会社の各社と相談の上、リスクの少ない
且つ節税効果を有無商品に変えていきます。
節税や運用でお困りの方は是非ご相談ください。

当事務所は墨田区を拠点に、東京、千葉、神奈川、埼玉の首都圏を中心に対応していますが、ご依頼があれば全国対応も可能です。
会計事務所での勤務経験と元システムエンジニアとしての経験を活かし、税務・経営相談だけでなく、業務効率化やシステムサポートなど、幅広いサポートを提供しています。
初回のご相談は無料、事前予約で休日・時間外の相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
Question:節税の為経費を使おうと思いますが良いでしょうか?
Answer
決算前の対策では良くある質問で、正しい効果的な節税は別の記事でご案内しますが、
今回は誤った節税をご紹介します。
節税=経費を使えばできる。
これは正しい考えではあります。
しかし、会社にお金が残らなくなるというのは耳にされたことがあるでしょうか?
これを以下の様に計算すると明白かと思います。
1,000万円の税引前利益がでたとします。
法人税が30%だとしたら、法人税は1,000万円✖️30%=300万円になります。
これを節税する為に、400万円の経費を使うとします。
経費を使った事で税引前利益は600万円になるので、
法人税は600万円✖️30%=180万円となりますので、120万円節税できた事にはなります。
良く考えてみれば、120万円の節税をする為に400万円のキャッシュアウトをしたわけ
なので、お金は実質は280万円も余計にお金が無くなったことになってます。
それであれば、300万円納税した方が280万円多く会社に残るわけです。
必要なものを経費として使うならば良し、従業員へ決算賞与を支給し、離職率を下げるの
も良しですが、単なる無駄遣いによる節税は効果なしという事です。

当事務所は墨田区を拠点に、東京、千葉、神奈川、埼玉の首都圏を中心に対応していますが、ご依頼があれば全国対応も可能です。
会計事務所での勤務経験と元システムエンジニアとしての経験を活かし、税務・経営相談だけでなく、業務効率化やシステムサポートなど、幅広いサポートを提供しています。
初回のご相談は無料、事前予約で休日・時間外の相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
Question:残高試算表は毎月作成した方が良いのですか?
Answer
年1で帳簿作成と申告依頼をご依頼頂くお客様から質問された内容となります。
試算表を作成する事で、入金漏れがないか等の経理に間違いがあるか確認する事ができます。
毎月試算表を作成する事で、売上・経費・利益がどの様になっているか等の経営状況が確認
でき健全な経営を行うには必要不可欠なものとなります。
また、金融機関からの融資の際は必ず必要なものとなり、その場しのぎで作成した試算表で
は融資もうまくいきません。
毎月の経営状況を社長が認識している事で、良くも悪くも融資面接の際には、社長がしっか
り経営状況を認識しているという加点要素にもなります。
さらに、年1での試算表作成では、大黒字となっていると効果的な節税も出来ません。
上記より、会社経営をする上で月次試算表を作成し経営状況を認識しておく事は当たり前の事です。

当事務所は墨田区を拠点に、東京、千葉、神奈川、埼玉の首都圏を中心に対応していますが、ご依頼があれば全国対応も可能です。
会計事務所での勤務経験と元システムエンジニアとしての経験を活かし、税務・経営相談だけでなく、業務効率化やシステムサポートなど、幅広いサポートを提供しています。
初回のご相談は無料、事前予約で休日・時間外の相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
Question:決算賞与を支給したいのですが今期の経費に計上できますか?また社会保険料も経費計上できますか?
Answer
利益が生じている会社では従業員への貢献を考慮し支給される、よくある決算対策
(決算賞与)ですね。
支給が決算対象月内であれば経費計上は可能ですが、支給が翌月になると注意が必要です。
従業員賞与については、支給日の属する事業年度に経費にするのが原則ですが 、以下の要件を満たせば、未払計上した従業員賞与を経費とすることができます。
例:3月決算法人が3月末の決算仕訳で決算賞与を未払計上し、支給日は翌期になる場合です。
①.損金算入の要件
(1) 支給額を各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての従業員に対して通知を
していること
(2) その支給額につき(1)の通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か
月以内に賞与を支給すること
(3) その支給額につき(1)の通知をした日の属する事業年度において損金経理を
していること
上記3要件を満たす決算賞与については、通知日の属する事業年度に経費処理(損金算入)
することができます。
では、さらなる決算対策として、上記①の要件を満たす未払の決算賞与について、
その社会保険料を未払計上して経費計上することは、結論を先に述べると、未払計上した決算賞与に係る社会保険料を未払計上しても、法人の支払債務が確定していないため損金算入することはできません。
法人税基本通達9-3-2にて、当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができるとされておりますが、賞与に係る社会保険料は支給を受けた日の属する月に標準賞与額に保険料率を乗じて計算する為、その標準賞与額が決定されるのは被保険者が賞与を受けた月ということになります。

当事務所は墨田区を拠点に、東京、千葉、神奈川、埼玉の首都圏を中心に対応していますが、ご依頼があれば全国対応も可能です。
会計事務所での勤務経験と元システムエンジニアとしての経験を活かし、税務・経営相談だけでなく、業務効率化やシステムサポートなど、幅広いサポートを提供しています。
初回のご相談は無料、事前予約で休日・時間外の相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
Question:法人化(法人成り)するメリットやタイミングを教えてください。
Answer
『法人化のタイミング』
法人化のタイミングは業種・売上規模・利益額・取引先規模・人員により、その方毎に大
きく異なりますので、端的に売上がいくらになったら法人化がお勧めとは言えない為、
面談等により詳細を聞かせて頂ければお答えが出来ます。
『メリット等』
法人化検討されるお客様の多くは信用力よりも節税対策を目的とされるが殆どかと
思います。
法人化によるメリットは簡単に申し上げますと以下の5つがあります。
①所得税の節税ができる
②家族の給与を経費にできる
③配偶者控除や扶養控除も受けられる
④赤字を出した場合は最大10年繰越できる
⑤消費税の課税事業者になるタイミングを遅らせられる
※ここでは1つ1つの内容のご説明は割愛しますので、ご興味があればご連絡を頂ければと
思います。
法人化=節税と考えがちですが、デメリットもあるので注意が必要です。
法人化をするデメリットは全部で4つあります。
①法人の設立必要がかかる
②社会保険への加入義務がある
③赤字でも住民税を支払わなければならない
④税理士を雇う必要がある
法人化やメリットデメリットでご質問のある方は面談やお電話等でご説明をさせて頂きます
ので、お気軽にご連絡下さい。

当事務所は墨田区を拠点に、東京、千葉、神奈川、埼玉の首都圏を中心に対応していますが、ご依頼があれば全国対応も可能です。
会計事務所での勤務経験と元システムエンジニアとしての経験を活かし、税務・経営相談だけでなく、業務効率化やシステムサポートなど、幅広いサポートを提供しています。
初回のご相談は無料、事前予約で休日・時間外の相談にも対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。